|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遺言者は、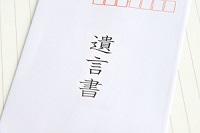 遺言者の居住地若しくは本籍地、または所有する不動産の場所を管轄する法務局(法務局の支局・出張所など)に対して自筆証書遺言の保管が申請できるようになります。これは、自筆証書遺言は自宅での保管が多いため、作成後の紛失や書き換えなどの心配や問題があったためです。相続が争続にならないようにするための制度の創設です。 遺言者の居住地若しくは本籍地、または所有する不動産の場所を管轄する法務局(法務局の支局・出張所など)に対して自筆証書遺言の保管が申請できるようになります。これは、自筆証書遺言は自宅での保管が多いため、作成後の紛失や書き換えなどの心配や問題があったためです。相続が争続にならないようにするための制度の創設です。
遺言者の死亡後に、遺言者の相続人、受遺者、遺言信託の受益者に指定 された方は、法務局(遺言書保管所)で「遺言書情報証明書」の公布申請ができるようになります。また、相続人の一人に遺言書の写しを公布したときや閲覧させた時は、遺言書保管官は他の相続人に遺言書が保管されていることを通知します。この制度の創設により、家庭裁判所での検認作業*は不要になります。 |
| *検認作業とは・・ |
家庭裁判所が相続人や利害関係者立会の元で、遺言書を開封してその内容を確認すること。相続のトラブルを未然に防ぐ意味があります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭請求が出来るようになります(特別寄与制度の創設) |
|
| 例えば子どもの配偶者(亡き長男の妻のような場合)などのように、相続人ではない親族が被相続人の看病や介護をした場合に以前は遺産の分配を受ける事が出来ないため、不公平だとの声が出ていました。今回の改正ではこの不公平を解消するために、無償で被相続人の看病や介護をし、被相続人の財産の維持や増加に特別な寄与をした場合には、相続人ではない親族も相続人に対して金銭の請求が出来るようになりました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相続での親族間のもめ事を防ぐためには遺言書を作成 しておくことが一番ですが、残念ながら無効になってしまう遺言書もあるようです。そのようなことにならないように、作成の際のポイントをお伝えします。 しておくことが一番ですが、残念ながら無効になってしまう遺言書もあるようです。そのようなことにならないように、作成の際のポイントをお伝えします。 |
| 1. |
遺言書には、遺産分割の内容を具体的に明記する(遺言書作成は自筆です)
例・・「私の所有する土地、建物を長女〇〇に相続させる」
「私の所有する預貯金は全額を長男〇〇に相続させる」 |
| 2. |
公正証書遺言は間違いがなく安心
公正証書遺言は法律のプロが作成する正式なものなので法的な間違いがなく安心です。お近くの公証人役場でご相談ください。 |
| 3. |
作成の際は、こっそり作成せずに相続人に知らせておく |
| 4. |
遺留分に配慮して、公平な遺産分割になるように心掛ける |
| 5. |
公平な遺産分割にならないときは、その理由や意思を明記しておく |
|
| 遺言書は残された家族への最後の意思表示です。財産のことは勿論、今までの感謝の気持ちなどを書いておくと、残された家族は故人への思いをより一層深いものにするでしょう。残された家族がトラブルなく相続ができるような遺言状作成をしたいものです。 |
|
|
|
| 参考:法務省発行「相続に関するルールが大きく変わります」 |











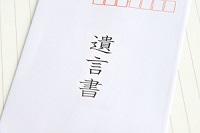 遺言者の居住地若しくは本籍地、または所有する不動産の場所を管轄する法務局(法務局の支局・出張所など)に対して自筆証書遺言の保管が申請できるようになります。これは、自筆証書遺言は自宅での保管が多いため、作成後の紛失や書き換えなどの心配や問題があったためです。相続が争続にならないようにするための制度の創設です。
遺言者の居住地若しくは本籍地、または所有する不動産の場所を管轄する法務局(法務局の支局・出張所など)に対して自筆証書遺言の保管が申請できるようになります。これは、自筆証書遺言は自宅での保管が多いため、作成後の紛失や書き換えなどの心配や問題があったためです。相続が争続にならないようにするための制度の創設です。 しておくことが一番ですが、残念ながら無効になってしまう遺言書もあるようです。そのようなことにならないように、作成の際のポイントをお伝えします。
しておくことが一番ですが、残念ながら無効になってしまう遺言書もあるようです。そのようなことにならないように、作成の際のポイントをお伝えします。 として明るい雰囲気に包まれました。子どもが浪人をすると決めたときは、長い人生の一年ぐらいの回り道はたいした事はないしむしろプラスになるよと子どもに言い聞かせてはみたものの、毎日の予備校生活は勉強で行き詰まる日があり友人関係で悩む日があり、また親子でぶつかる日もありで、この一年間は支える側も気を揉みました。そんな日々を経て、子どもはやっと私の手元を離れ、東京の女子大生になりました。
として明るい雰囲気に包まれました。子どもが浪人をすると決めたときは、長い人生の一年ぐらいの回り道はたいした事はないしむしろプラスになるよと子どもに言い聞かせてはみたものの、毎日の予備校生活は勉強で行き詰まる日があり友人関係で悩む日があり、また親子でぶつかる日もありで、この一年間は支える側も気を揉みました。そんな日々を経て、子どもはやっと私の手元を離れ、東京の女子大生になりました。