|
|
|
 |
法定後見制度について |
|
|
|
本人の判断能力が衰えた後に家庭裁判所によって後見人などを選んでもらう制度です。法定後見制度は、「後見」・「保佐」・「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度が利用できます。
法定後見人制度は、家庭裁判所によってえらばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら本人の代理となって法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消す、などで本人を保護・支援していきます。 |
|
|
|
 |
任意後見制度について |
|
|
|
任意後見制度は、本人の判断が充分なうちに、判断能力が衰えたときに備えて後見人を自分で選定し契約しておく制度で、後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事柄について、家庭裁判所が選ぶ「任意後見監督人」の監督のもと本人の代理となって契約などの履行が可能になり、本人の意思に基づいた適切な保護・支援ができます。 |
|
|
|
 |
成年後見人などの選任について |
|
|
|
成年後見人などは、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家やその他の第三者、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれることがあります。成年後見人などを複数選ぶこともできます。また、成年後見人などを監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
なお、後見開始などの審判を申したてた人において特定の人が成年後見人に選ばれることを希望していた場合であっても、家庭裁判所が希望どおりの人を成年後見人などに選任するとは限りません。希望に沿わない人が成年後見人に選任された場合であっても、そのことを理由に後見開始などの審判に対して不服申し立てをすることはできません。 |
|
|
|
 |
成年後見人などの役割について |
|
|
|
成年後見人などは、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の周りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人などの職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られていて、食事の世話や介護などは、成年後見人の職務からは外れます。
また、成年後見人などはその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。 |
|
参考…「自分のために みんなの安心 成年後見制度」法務省 |











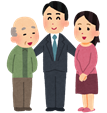
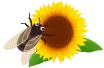
 夏になりました。そして、子どもたちは夏休みです。今年は特に暑く、宮崎はまるで亜熱帯に属しているのかと思うほどです。日が落ちて夜になってもまた朝になっても、むっとした熱がこもっています。
夏になりました。そして、子どもたちは夏休みです。今年は特に暑く、宮崎はまるで亜熱帯に属しているのかと思うほどです。日が落ちて夜になってもまた朝になっても、むっとした熱がこもっています。